中立の立場で客観的に判断する中枢部
クライアントに近すぎても、生産部や品質管理部に近すぎても、いい製品はできません。
あくまで中立な立場で、生産を管理します。

仕事内容
生産する上で、必ず原価と売価のギャップ・生産効率・ロスの問題が出てきます。
いかにしてそれらの問題を縮小し、生産効率を上げる方法を客観的に判断・検証するのが原価調整室の仕事です。
管理は多岐に渡り、企画と現実とのギャップ・人の配置・材料の管理・生産スケジュールまで隅々まで目を凝らして見ていないといけません。
当然、どこの過程にも人が居ますので各部署間で意見がぶつかり合いになることもしばしば。
そこでクライアントにとっても、ファウンテンデリにとっても良い製品を作るためにはどうすればいいのかを、中立の立場で判断し、
客観的な数字のデータを元にして課題を一番いい形で納めるために注力するのが私たちの腕の見せ所です。
寸分の隙も無いデータ化管理
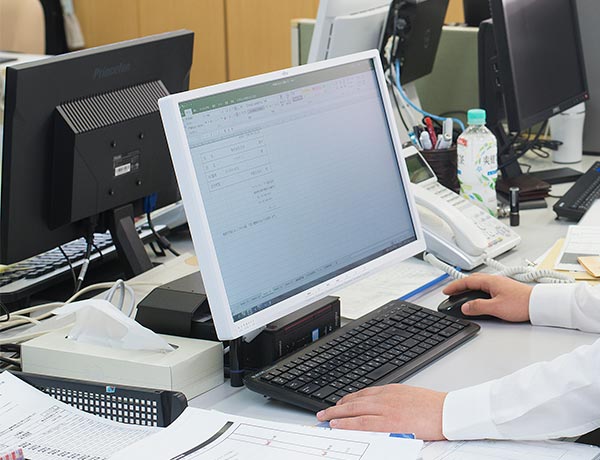
原価や食品ロス・人件費等、数値管理が必要なものを専属で管理しています。
新商品は販売前に約100~500食での製造のテストを行います。その際に、規格書で示されている歩留で実際に製造可能か、人件費は問題ないかなどを事前に確認することが利益を生む為には重要となります。
原材料の状態や気候、機械によっても歩留は異なるため、一番ベストな数値をつかむ事は食品ロスの削減にもつながる事になります。
例えば、鶏そぼろの規格が歩留90%の場合、鶏肉10kgから9kgの鶏そぼろができる事になります。
しかし、歩留が実際には91%だった場合は100gの廃棄が、89%だった場合は100gの不足が発生する事になります。
1%はたいしたことではないように思われますが、大量に生産する上では、1%の誤差があると大きな影響が出ることになります。
歩留を把握することは大変重要なことなのです。
また、利益を出す為には人件費を抑えていかなければいけません。テスト時にトッピングを実際に行い、効率的に作業ができる方法はないか、冶具を使用することで人件費の削減ができないかなども数値的に検証します。
同時に、品質に問題ないか、規格書どおりの商品ができているかを確認し、販売時には最善の方法での生産ができるよう、各部署と協力して取り組んでいます。
実際に販売開始した後も、生産現場からさまざまな数値をあげてもらい、確認・検証を実施、各関係部署に都度報告し、歩留を変更するなど、さまざまな業務改善に日々努めています。
その数値をまとめ、分析し、商品開発部と共有することで商品を開発する上でも有効に活用することができます。
ムダを無くし生産性を高める原価調整室

人の配置だけではなく、教育にも力を入れています。現在、ファウンテン・デリで働く従業員の約半分が留学生などの外国人です。通訳を通したその場限りの教育ではなく、日本と海外の「食」に対する認識の違いや生産している商品について理解してもらえるようにカリキュラムを組み、外国人正社員3名を中心にしっかり教育していくことを大切にしています。
「会社=人」を念頭に、商品開発部が開発した大切な商品を、大量生産と品質の徹底とを両立しつつ生産していくためにはどうすればよいか、また、今までの経験を数値的に把握し、次の開発に役立てるにはどのようにすればよいか、各部署と連携を取りつつ原価率の低減を目指します。